サロンとは何か
宇野重規
サロンとは何だろうか。希望学サロンを開始するにあたって考えてみた。
ためしに Wikipediaで引いてみたら「フランス語で宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界をサロンと呼んだ。主人(女主人である場合も多い)が、文化人、学者、作家らを招いて、知的な会話を楽しんだ。フランスではヴェルサイユ宮殿を中心に、いくつものサロンが開かれた。ラ・ファイエット夫人やポンパドゥール夫人らのサロンなどが史上有名。啓蒙主義の思想家たちもサロンの交流で、思想を深めていった」とある。「社交界」、「文化人」、「知的な会話」など、ちょっと気恥ずかしくなるような言葉が並んでいる。正直なところ、希望学の目指しているものとは、ちょっとずれているという気もする。 が、そう結論を急ぐことはない。いま、ここに参考になりそうな本がある。赤木昭三・赤木富美子 『サロンの思想史−デカルトから啓蒙思想へ』(名古屋大学出版会)だ。サロンというと、ややもすれば特権階級の知的遊戯という印象があり、表層的で軽佻浮薄といったイメージを感じる人も多いはずだ。しかし、この本は、そういった印象を吹き飛ばし、サロンが「思想の伝播、交流、そして創出の場」であったと論じている。著者たちによれば、17・18世紀のフランスにおいて、大学などが、伝統的なカリキュラムにしばられ、新しい知的動向に対しきわめて保守的であったのに対し、新しい知を求める人々によって直接的な交流の場が求められていた。そのような要請に応えたのが、サロンであった。 著者たちのサロンの定義をいくつか見てみよう。まず、「サロンとは、会話をもっとも重要なコミュニケーションの手段とするひとつの社交形態である」。あくまで会話が重要というのは、ポイントかもしれない。それは、「開かれた社交形態」であり、なかば「公共的な空間」である。なぜなら、そこには、常連だけでなくつねにゲストが出入りし、「他の団体とくらべて、職業、社会階層などの社会的出自に広がりがあ」ったからだ。また興味深いのは、「女性が社交の中心となる」点であった。これは女性の参加を認めなかったクラブやフリーメーソンなどとは違う、サロンの大きな特徴であった。
さらに、著者たちは、サロンから生まれた独自の人間像として「オネット・オム(正直な人・誠実な人)」を紹介している。この言葉はもちろんイギリスの「ジェントルマン(紳士)」に対応するものだが、サロンという場の理想をよく示している。「オネット・オム」はなにより、他の参加者と自然に交われる節度ある人間を指すが、それと同時に、普遍的な「人間」の立場に立つことを意味するという。「オネット・オムはすべてを知るが、なにかをメチエ(職業)にして自分を特殊化することはない。彼は何の専門家でもなく、まさしく「人間」であり、「人間」の立場で考え、判断する。そしてこのような普遍的な「人間」であることによって、彼は身分や国家、さらには時代を超えて「世界の市民」となる」。
あまり、たいそうなことをいうと、後で自分たちの首を絞めそうだから、これくらいにしよう。ただ、「専門家」である前に、一人の「人間」として参加する、というのはサロンの本質かもしれない。もちろん専門の視点は重要だ。が、その場合も、何々の専門家であるとして自分を「特殊化」してしまう前に、まず一人の人間として考え、判断すること。これがサロンに求められている態度なのかもしれない。
ちなみに、ジャン=ジャック・ルソーはサロンにあこがれ、そこに入り適応するためにずいぶんと努力もしたようだが、最後まで空気になじめなかった。「自然に帰れ」とルソーが言ったかはともかく、ルソーにとって、サロンという場所は偽善的で虚飾に満ちたものに映ったことは間違いない。それでも、彼の作品や、彼のサロン批判を評価したのもまた、サロンの女主人と常連たちだった。そのくらいサロンの影響力は大きかったのである。
はたして希望学サロンが、「思想の伝播、交流、そして創出の場」になるかどうかはわからない。が、少なくとも、これまでの大学の場にはなかった新しい交流の機会となり、新しい知を模索し一人の人間としてものを考えたいという人の集まる場になるといいと思う。
< 参考文献 >
『サロンの思想史—デカルトから啓蒙思想へ』赤木昭三・赤木富美子(著)
名古屋大学出版会 2003年9月 3,800円
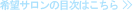
↑PAGE TOP
|