第2回 寺山修司
「人類が、最後に罹るのは、希望という病気である」
鬼才・寺山修司がこの言葉を初めて眼にしたのは、彼が34歳になる1969年、学生紛争で荒れ果てた東京大学法学部研究室内であった。「機動隊が、学生たちの最後の砦になっている安田講堂に向かい、ときおりガス銃を発射する音がこだましてくる」廃墟の中で、一人ぼんやり腰をおろし、ふと懐中電灯を照らした先に、この言葉があった。
「人類が最後に罹るのは、希望という病気である」という言葉を残したのは、『星の王子さま』を書いたサン=テグジュペリであった。彼は、いくつかの絵と文を書いた後、第二次世界大戦中、愛用の飛行機ごと行方不明になって死んでいった。荒れ果てた東大法学部の教室で出会ったこのサン=テグジュペリの言葉を、寺山はその後折りに触れて引用している。「大空に消えたこの飛行家は友人もいたし、愛すべき家庭も思想もあった。だが、私たちはこうした時代を通りすぎて、さらに長く生きながらえたばかりに、希望という病気にさえも、罹ることがないのである」では寺山は、「希望という病気にすら罹らない」私たちへどんな言葉を投げかけ、何を望んだのであろうか。
寺山修司は、1935年12月10日青森県弘前市紺屋町に父・八郎、母・はつの長男として生まれた。父の当時の職業は刑事であり、小学生時代は青森県内を数回にわたって転校した。母はつは、寺山を溺愛し、「少年倶楽部」や「少国民の友」を買い与える一方で、その雑誌に寺山が没頭すると烈火のごとく怒り本を取り上げて火中に放り込む、という激情を持つ人間であった。終戦となる1945年7月28日、青森市は大空襲に遭う。寺山は母と共に焼夷弾の雨をくぐりぬけ、奇跡的に火傷もおわず生き延びる。後年寺山はこの経験を「少年時代の三大地獄の一つ」に数え上げている。「私は、父が出征の夜、母ともつれあって、蒲団からはみださせた四本の足、赤いじゅばん、20ワットの裸電球のお月さまの下でありありと目撃した性のイメージと、お寺の地獄絵と、空襲の三つが、私の少年時代の『三大地獄』だったのではないか。」
終戦後、空襲で焼け出された寺山母子は、父の兄を頼り、父の郷里である青森県三沢市へ身を寄せる。そして同年9月2日、父がセレベス島で戦病死したことを知るのである。父の遺骨が郷里に届いた日、母は洋裁ばさみで手首を切って自殺をはかり、寺山にも無理心中を強いた。その夜、寺山は母が嘔吐した吐瀉物を捨てに川まで行った。
「波止場まで嘔吐せしもの捨てにきてその洗面器しばらく見つむ」
寺山、10歳の秋の出来事である。
はつは、やがて三沢の米軍キャンプ内に勤め始める。アメリカ兵が家まで母をジープで送り迎えするようになり、寺山は「低い階級の労働に甘んじている」と感じ、自身を「かくれずには、いられない」と「かくれんぼ」遊びに熱中するようになった。
1948年4月、寺山は青森県古間木中学へ入学。同年秋に、母は福岡県遠賀郡芦屋町にある米軍キャンプへ出稼ぎに行くことになり、寺山は青森市松原町で映画館を営む叔父の家に引きとられる。
青森市野脇中学校へ転校した寺山は、俳句や短歌などを発表し、その才覚を現していく。
「菜の花の咲ける畑の月の出に病める子の吹くハーモニカの音」
「桐の花白く静かに落ちる時悲しくめぐる君が思い出」
寺山16歳、青森県立青森高校へ進学。自ら「青森高校文学会議」を組織し、全国詩誌「魚類の薔薇」を編集発行。また次々に俳句雑誌へ投句し、「墜落したら俳句ができた」等とメモに記し、俳句によって「自己形成を記録」していった。俳句に熱中する一方、寺山は叔父の経営する映画館で金田というボクシングジムに通う映画技師と親交を深めていった。金田が貸してくれた本に「勝つことは思想である」という文言が書かれており、寺山はこの言葉に深く心を打たれた。
1954年、寺山は早稲田大学教育学部国語国文学科へ入学し、「東京」に住むこととなる。しかし、寺山は入学まもなく「大学とは『他人の話を聞く』ところにすぎなかった」と大学に対する失望を露わにする。寺山にとって上京してからの最大の「学問的感激」は、東京一周の「はとバス」であった。「はとバスもまた、ガイドによる講座制にはちがいないが、自分たちが啓蒙されつつある現実のなかを走りぬけてゆくという快感」があったのだ。東京での大学生活を通して寺山は「物理学と因数分解と西洋史年表にたけた高校生の私が、日本人としてどのくらいの生活基準にあり、将来何を選択するべきなのか無知でいられる」ということに対して、大きな危機感を持ったのだった。
そして大学入学と同時期に、本格的に短歌界へと躍り出、注目を浴びる。
「海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり」
「耳大きな一兵卒の亡き父よ春の怒涛を聞きすましいむ」
しかしこの時期、ネフローゼの症状が出る。ネフローゼとは、「尿の中に大量の蛋白がもれてしまうために、浮腫や血中の脂質の上昇がみられる状態」であり、放置しておくと肝機能が徐々に低下してく場合がある。1955年6月に新宿区の社会保険中央病院に入院、一時は危篤になるほど寺山の症状は重かった。入院中寺山は、彼の信頼する友人や恩師と文通を繰り返した。
「コロッケは食べましたか。元気ですか。(中略)今日位、いい天気の日は、川が海へゆくように、鳥に空のあるように、僕はあの子。一寸立寄ることがそんなにいやなのだろうか。僕はにぶくないし、今、あの子は僕と橋を架けたくないことだって知っている。でも、話すことは、それくらいは、と思う。ああ醜悪なるロミオ。畜生。手紙くらいはよこしたまえ。同情せよ。」(友・山田太一へ宛てた葉書、1956年4月21日)
「どうもありがとう。サルトルのネクラソフ、アメリカ論。カーの浪漫的亡命者たち。クロポトチンのフランス革命上中下を買い、4千円を蓄音機への貯金としました。」(恩師・中野トクへ宛てた葉書、1956年5月21日)
退院後の寺山は、俳句や短歌だけでなく、ラジオやテレビドラマ、そして戯曲へとその表現形態を広げていく。まるで今までの絶対安静生活を取り戻すかのように、執拗に着々と様々な「表現」を試みていくのだ。その中の一つ、60年安保の年に書いた、ラジオドラマ『大人狩り』が、革命と暴力を扇動する恐れがあるとされて、公安の取調べを受ける。寺山の「表現」の傍らには常に私たちが生きている社会が寄り添っていたといっても過言ではないだろう。
1967年演劇実験室「天井桟敷」を設立した寺山は、その奇才ぶりを遺憾なく発揮していく。「〈怪優奇優侏儒巨人美少女等募集〉と銘打って、〈見世物の復権〉をねらった」この演劇実験室「天井桟敷」の設立は、一見「珍奇なアイデア」ではある。しかし、実はその裏には「自分を不幸だと思う人間は、その不幸を表現すべきだ」という「大胆なネライ」があった。つまり、「昔のように、食えない、という純粋に物質的な不幸と違って、今日の不幸は、たぶんに、自分は周囲から見捨てられている人間である、という精神的な飢餓感の形」をとって現れるため、「『自分はこんなに不幸だ!この不幸な自分を愛してくれ!』と大声をあげて、周囲の視線を自分に集めること」こそ、幸福を回復する一つの手段だと考えたのである。事実、10代20代の頃の寺山は、自身の不幸を繰り返し、あの手この手で声を大にして叫んだ。「俺は不幸だ、俺の不幸は母に捨てられたことだ」と。そして、自身の「不幸」を表明することで、自身を救ってきたのだ。
しかし、「天井桟敷」を設立し、暫くして70年安保が起こり、様々な青年達と関わっていくうちに、寺山ははたと気がつく。現代の青年達は「淡々として、平和で無事に生きてきわめて健康で、しかし友人も自己認識もなく(不安も恍惚感もなく)生きている」のだ、と。寺山は言う。「こんな時代の青年たちを、どうして私たちは仲間だと思うことが出来るだろうか?」「希望」という病気に罹るために寺山が青年たちにおくった言葉が「冷淡な健康よりは、やさしい病弱さを」だ。
寺山は言う。
「目を醒まして、歌え・・・ドラマには終わりがあるが、人生には終わりがないのです」
<参考文献>
栗坪良樹編集・評伝(1993)『新潮社日本文学アルバム 寺山修司』新潮社
サン=テグジュペリ(2000)『星の王子さま』内藤濯訳 岩波書店
寺山修司(1973)『幸福論』角川文庫
寺山修司(2000)『ぼくは話しかける』ハルキ文庫
塚本邦雄(2003)『麒麟騎手 寺山修司論』沖積舎
文責:佐藤由紀(東京大学大学院学際情報学府)
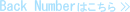
↑PAGE TOP
|