第1回 魯迅
「絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じだ」
魯迅がこの「希望」という題名の日記を書いた日付は1925年1月1日となっている。中国では正月は旧暦を祝う習慣があるため、この日、特別なお祝いごとはなかったものの、魯迅は数名の友人たちと共に昼食会を開いた後映画を観に行き、遅くに帰宅した。また、この頃の魯迅は、様々な大学へ講義に出かけ、執筆活動も活発におこない、青年文学者たちの育成に力を注ぎ、多くの友人たちと食事を共にしていた。活動履歴だけを見れば、人間の力を信じ、活発に動いていた頃の魯迅の口からでた「希望」についての、この謎めいた文言。一体魯迅はどのような思いを抱えて、この文言を記したのだろうか。
魯迅は1881年、地方の旧家に生まれる。裕福な家に生まれた魯迅にとって、将来の安定は約束されたようなものだった。しかし魯迅が13歳となる年、祖父が収賄容疑で捕まり、次の年には父が吐血、肺病と診断された頃から彼の人生は大きく変化していく。様々な困難や貧困、偏見と闘いながらも彼は南京の学校へと入学後、官費の留学試験を受けて合格し、日本へ留学する。日本において、はじめは医学の道を志すが、ある授業でスパイをした中国人に対する処刑に同じ中国人が「万歳」と叫んでいる画を見、医学では中国人の精神は変わらないと感じ、文藝活動による啓蒙活動を思い立つのである。その後、中国に戻った彼は、執筆活動を開始する。清朝を滅ぼすことになった辛亥革命、袁世凱が孫文を排斥した第二革命、袁世凱の帝政運動、ベルサイユ条約拒否を求めた五四運動等が次々と起こっていく中国激動の時代を体験しながら、魯迅自身も多くの小説や雑感文などを精力的に発表することによって啓蒙活動を進めていく。この時代に発表された「未荘という農村の地蔵堂に住み,日雇いの賃仕事に雇われているが,その生き方はその場しのぎであり,かつ自己欺瞞的」な亜Qという男を主人公にした「阿Q世伝」は、当時の彼が憂えた「中国農村の前近代的な実態や,阿Q的人間に象徴される中国知識人や,軍閥などの姿が諷刺的に示されて」いる。
これらの精力的な執筆・啓蒙活動後の1925年、魯迅は44歳となる年にこの「希望」という散文詩が書かれることになる。この頃、彼は自らが活動することよりもむしろ、後継者となるべく青年文学者たちの育成へ、その心血を注ぎ込み始める。
何度も何度も真の革命という理想を夢見、希望し、もう少しで手が届くかと思うたびに、裏切られ、家族や仲間の命さえも奪われてきた魯迅。彼は、ハンガリーの詩人、ペテーフィの歌を引用する。
「希望とはなに?娼婦さ
だれをも魅惑し、すべてを捧げさせ、
おまえが多くの宝物-おまえの青春-を失ったとき、
おまえを棄てるのだ」
魯迅はこの詩を引用し、「希望」が所詮は「虚妄(うそいつわり)」でしかないことを確認するのである。実際、魯迅自身幾度となく「希望」を抱き、そしてその「希望」に裏切られてきたのだ。
「しかし痛ましき人生よ!傲岸不屈のペテーフィのごときも、ついに暗夜に向かって歩みを止め、茫々たる東方を振り返っているのだ。かれはいう。
絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じだ」
確かに「希望」は「虚妄」でしかない。では「絶望」はどうだろうか?
と、魯迅はここで問い直す。あの「傲岸不屈なペテーフィでさえも、『茫々たる東方』(夜明け)を振り返って『絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じだ』と言っている」のである。つまり、「真夜中」=「絶望」にも夜明けが必ずやってくるように、絶望もやはり「虚妄」なのだ。魯迅にとって、「絶望」を知る者こそ「希望」を知ることが出来るのだ、という思いが、ここに隠されているのである。
現にこの文言の後、
「だが暗夜はいったいどこにあるのか?いまは星はなく、月光および笑いの渺茫と愛の翔舞もない。青年たちはとても平安だ。そして、わたしのまえにはついに真の暗夜さえないのだ」 と、魯迅は1925年当時の青年文学者たちに対して、彼らが安穏とした平安に甘んじ、「絶望」を感じる場所へさえ立っていない、と嘆いている。「真の暗夜さえない」、つまり、「絶望を感じることのできない無感覚な状態」なのだ。闇夜を知ってこそ、光が来るのだ。
そして魯迅はもう一度くりかえす。
<参考文献>
片山智行(1991)『希望』(魯迅「野草」全釈)平凡社
高田昭二(1982)『魯迅の生涯とその文学』大明堂
文責:佐藤由紀(東京大学大学院学際情報学府)
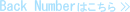
↑PAGE TOP
|