風が通りすぎる街
佐藤義行
わたしなりに、ふるさと釜石をひと言で表わしたことばだ。
「鉄」の町でも、「魚」の町でもない。たしかに、わたしが生まれる前から製鉄所も、魚市場もあった。でも、それはふるさとのイメージそのものではない。
風。あれだけ山に囲まれていながらどうしてあんなに風があるのだろうか。夏には、冷たい白い風が海から山へと向かっていった。冬には、かじかむほどに寒く、強い風がビュービュー吹いていた。春には、山の芽吹きの香りをかすかに帯びたやさしい風が、秋には夕焼け雲を動かしている穏やかな風が吹いていたような気がする。風の強い夜には、木枠の窓ガラスがゴトゴトいう。なかばおびえながら、わたしは7人の家族と食卓を囲み、父母のむかしばなしに耳を傾けながら眠りについていた。風が吹いている外とは対照的に、家の中は温かく穏やかだった。
風はいろいろな音を運んできた。貨物船の汽笛、製鉄所のゴーンという大きい音、間の抜けた貨車の警報機の音、愛の鐘や石応禅寺の鐘...。思えばすべて釜石ならではのものばかりである。
汽笛や製鉄所の音が聞こえなくなったのは、いつの頃からだろうか。昭和40年代生まれのわたしにとって、その音こそが釜石発展の証だったのかもしれない。
好景気に沸き続けていた昔のことは、両親をはじめ大人からいやというほど聞かされてきた。しかし、子どもであるわたしにとっては何の意味もなく、ふーんという感じだった。単にむかしばなしでしかなかったし、昔に戻ることを、それも行政にそれを期待しているようにしか感じられなかったからだ。
中学から高校時代にかけて、親戚や友人、近所の人がどんどんいなくなっていったような気がする。その人たちが、希望をもって釜石を出ていったとはわたしにはどうしても思えない。千葉や名古屋の暑さを心配する人、何もいわずに出ていってしまう人、年をとった人は食べ物の心配ばかりしていたような気がする。なんだかんだいいながらも、みんな好景気に沸き続けていた北の海辺の町が好きだったのではないだろうか。3月の釜石駅では、あの風が吹きっさらしのホームで列車が出るたびに万歳と蛍の光がかかって、列車が出るとすぐ、足早に風を避けるべく地下通路に駆け込んでいた。そして、誰もが次は自分の番だと思っているようだった。この光景を思い出すとどうしても希望には結びつかないのだ。
釜石を出て、20年近くなる。よくふるさとが変わってしまったということを耳にするが、釜石はほとんど変わっていない。このドッグイヤー、マウスイヤーといわれ、激動している日本では極めて珍しいのかもしれないし、変わってほしくないと願うわたしとしては嬉しい。しかし、人のこころは変わっているような気がする。むかしを懐かしむ声はほとんど聞かないし、もう戻ることはないと思っているようだ。今が不景気なのではなく、これが普通だと感じられるようになっているのだ。聞けば、釜石に残る若い人がけっこういるという。もしかしたら、他人任せの、希望が見出せないという風が通り過ぎ去ったのかもしれない。
釜石には過去、さまざまな試練があっと思う。わたしの祖父は昭和8年の津波で家財を失い仕事を変えることを余儀なくされた。母は今でも夏の花火を嫌う、理由は艦砲射撃を思い出すからだうだ。かくいうわたしも子どもの頃は喘息を患っていた。しかし、その試練の風をじっと耐え、受け入れ生きてきたのが釜石の人なのだ。
わたしは、自分の出身地をいうとき、すんなり岩手ということができない。釜石といってしまう。それは、釜石がどこの町とも似ていないからだ。
「名物は何か」とも聞かれる。
「何もないなぁ」といいつつ、普通に食卓にのぼるメカブやマツボ、タラッポ、アブラメ、サンマ、カゼ、ハランコが頭に浮かぶ。名所もない。水海海岸の上を通る45号線からみる三貫島、魚市場から見た朝日、尾崎半島、閉鎖的に感じられる北上高地と水平線の見えない海……。わたしにとってすべてが日常の風景、名所ではない。
わたしは釜石の日常が好きだ。釜石のよさは何気ないところにあり、つかみ所のないような風のようなものなのではないだろうか。
釜石にはつねに風が吹いているように思う。これからも吹き続けるだろう。追い風かもしれないし、向かい風かもしれない。その風が希望を運んでくれることを願ってやまない。
佐藤 義行(釜石市出身、37歳)
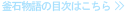
↑PAGE TOP
|