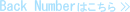『季刊 健康』2005年冬号(2005年12月1日発売)
希望を科学する
玄田 有史
「健康を科学する」というのは、たしかどこかの薬品メーカーの宣伝文句だったと思うが、今、私たちは「希望を科学する」という取り組みを始めている。「私たち」というのは、私が現在所属している東京大学の社会科学研究所にいる仲間たちのことだ。
希望の科学などというと、何やら宗教関係の団体のようにも聞こえなくはないが、私たちが目指すのは、そんな団体や学会の設立ではない。希望とは何か、希望と社会とのかかわりはどうなっているのかといった事実を、データ収集やインタビュー調査などによって、明らかにしたい。だから、希望を社会の問題として科学的に考える希望の社会科学を、私たちは「希望学」と名づけることにした。
今、社会には「希望がない」という言葉があふれている。その最も象徴的な存在が、ニートと呼ばれる働くことに希望が見出せないまま立ち止まってしまった若者たちだ。どうすれば若者たちが働くことに、そして生きることに希望を見出すことができるのか。
希望という個人の心理や感情と深くかかわる問題に、科学といえるような客観的な普遍性や法則があるのか疑わしいという意見も希望学には寄せられる。そもそも希望を持つことは、本当に意味すらあるのかと。人によっては、希望なんて考えること自体が一種の贅沢病とさえ言われた。
希望学の仲間は、有名な経営者だった老人から、こんな話をうかがったことがあるという。若き日に大東亜戦争に徴収され、戦地で死の淵を何日間も彷徨った経験を持つその人は、自分が生き永らえることが出来たのは、その極限状況で、一切希望を持たないようにしたことだという。希望を持とうとした仲間ほど、結局は現実に絶望し、自ら命を絶っていったのだと。
反対に、希望を持つことが個人の生き方に明確な影響を及ぼすことがある。東京大学の上別府圭子先生から教えていただいたのは、そんな看護学の研究論文だった。ガンの再発を告知された患者は初発の患者に比べても大きな希望の喪失感を味わう傾向がある。しかし、そんな再発患者とその家族に、希望を高めるような主々の適切な看護措置を講じることで、実際に生きる希望を高め、生命の質(QOL)を改善することも可能だという。
健康には、適切な生活習慣と、ときには適切な医療措置が欠かせない。ただそれと同時に、生きる希望を保ち続けることも、健康のための重要な条件というのは示唆的だ。
希望は持つべきか、持たざるべきか。そこに唯一の答えは存在しない。古くから多くの著述家が指摘するように、希望はその多くが、失望もしくは絶望に終わる。絶望を見たくない人は希望から敢えて目を背ける。そうしなければ生きていけないこともある。
問題は、何かに深く絶望したとき、そこに新たな希望を見出せるような、人とのかかわりがあるかどうかなのだろう。希望が絶望に変わったとき、そこで個人を孤立させない社会。それこそが健康な社会なのだと私は思う。