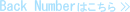『東京大学新聞』(2005年10月11日発行)
学問で「希望」を追う
希望学プロジェクトが明かす「希望」の全貌
知識と研究技法の交流が可能に
7月15日、社会科学研究所が「希望学宣言!」というシンポジウムを行った。これは、社研が「希望学」という共同研究の開始を社会に向けて広く宣伝したもの。「希望」という誰にでも関係のあるテーマを扱った研究には学外から多くの反響があったという。新しい学問がどのような経緯で生まれ、そしてその狙いは何なのか。社研の取り組みを追った。(取材・上原聡史)
明るい話題の研究を
■様々な立場から
64年から5年に一度、社研では研究所の教員のほとんどが一つのテーマについて共同で研究する「全所的プロジェクト」が行われてきた。「基本的人権」「戦後改革」など、プロジェクトで扱われるテーマはどれも様々な視点で分析できるもの。テーマをいくつかの内容に分け、その中で問いを立てた後に、研究者同士が発表・議論を通してその答えを探る。法、政治、経済など、社会科学の主要な分野を専門とする社研の研究者全員が共同で行う取り組みだ
前回のプロジェクト「失われた10年?」は、暗い話題ばかりの日本社会を見直すため、国際的枠組みや金融、長期的構造変化などをテーマにした硬い研究だった。教育社会学を専門にし、プロジェクトに関わる佐藤香助教授(社会科学研究所)は、「視点を少し変えて、なぜ明るい話題がないのか、という問題意識から出てきたのが今回の『希望学』だった」と話す。
■手探り状態の研究
「希望学」の特徴は「問題ありき」であること。社会科学の研究では多くの場合始めに仮説があり、それを検証していく。問題を立てても、答えはあらかじめだいたい予想でき、そこに行き着く研究手法が決まっていることがほとんどだ。しかし、今回の場合「希望はどのように形成され、一方で失われるのか」という強い問題意識があったものの、答えはまったく予想ができず、研究の方法も一から考える必要があった。
今回のプロジェクトでは、まず始めにシンポジウムを開催した。シンポジウムでは、研究を始めるに当たって、希望学に関した講演や対談が行われ、合計で271人の人が集まった。研究成果の発表の場として利用されることの多いシンポジウムだが、希望学の場合は、立ち上げを告知する意味合いが大きい。「アンケート調査などが基本となる今回のプロジェクトを社会に宣伝し、広く研究への協力を求めるという目的があった」(佐藤助教授)
職業と希望の関連から研究
■無理が成果生む
研究者は、それぞれ異なる専門を持ち、その研究手法も異なる。それゆえ、研究所全体で研究を行うことで、そうした違いが障害となることもある。しかし一方で、「他の研究手法を持つ人と、議論をすることで新たに発見することもしばしば」と経済史を専門にする中村尚史助教授(社会科学研究所)は語る。研究者が自分の知識や研究様式を持ち寄って、希望についてどう分析できるかの知恵を出し合う。各自が普段と違う方法で研究を進めるなど困難は多い。その代わり、研究はこれまでにないようなものになった。
■社会へ発信する
プロジェクトは、ウェブ上での前調査を終えたところだ。今年5月に、20〜40代の人を対象に「職業と希望の関係性」についてウェブサイト上でアンケートを行った。今後、この結果を踏まえて、より多くの人に対して本調査を行う。また、前調査の結果、希望と仕事が密接な関わりを持っていることが明らかになった。それ以外の要因で人がどのように希望を持つか、世代別の調査などを進めていく予定だ。「まだ、成果については未知数の部分が大きいが、年内にはその大まかな方向性を決定したい」(佐藤助教授)
また、心理学や医学も希望を考える上で大きな位置を占める。附属病院や他の研究科の研究者との連携も重要になる。「希望学」は、漠然としたテーマではあるものの、テーマが多くの人にとって関わりのあることであるがゆえに社会での注目度も高い。学問分野が高度に専門化している状況への反発もこの取り組みには込められているという。
研究者が書く論文は専門的であればあるほど、それを読んでもらう対象は限られる。しかし、本来「社会科学は、社会のごく普通の人が対象となるべき学問」(佐藤助教授)だ。社会との関わりという観点からも、取り組みの意義は大きいだろう。
ことばファイル「希望学」
「希望を社会科学する」を合い言葉に、希望を社会全般にとって無くてはならないものとして捉え、その社会的意味を明らかにする学問。経済、政治、歴史などの視点から、希望がどのように形成され、また失われるのかを探る。研究は社会科学研究所の教員らが中心となり、報告会・意見交換会を通して進められる。