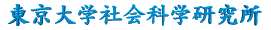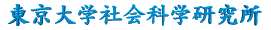|
【橘川 武郎】 1990年代の日本社会をめぐって
→
【討論】
II.「構造転換」が問題化する構造
今回のプロジェクトでは、対象は共通だが、一つのシェーマで括ることはしない。
冷戦体制の崩壊と、アメリカ経済の非常な好調とが、現在の世界を動かしている基点である。この二つは別々の事柄だがこれが合わさって、アメリカ主導の世界的な構造調整が起きていて、いろいろな地域で問題を引き起こしている。今回のプロジェクトでは、この1990年代における構造調整の、各地域における作用と反作用を主たる対象とする。
取り上げる地域はヨーロッパ、旧東欧・日本・アジア・ラテンアメリカである。
-
ヨーロッパ統合は構造調整以前から進展しているが、現在の事態の中で新たなイシューが起こっているかどうか。
-
東欧等旧社会主義国では資本主義化が90年代に起こり、アジア・ラテンアメリカは、経済成長とその頓挫が、日本では長期不況が問題となる。
二つのキーワードとその帰結
上のような変化をもたらしているメカニズムを経済・経営から見ると次の(1)(2)がポイントとなる。
1.市場主義(規制緩和等)
6月セミナーの澁谷報告では、アメリカは力を背景に世界に市場論理の純粋型を発信していて、そのインパクトは非常に強い、ということが言われた。インパクトを受ける側からいうと、仕組みを変えなければならない、という問題となる。
2.競争の焦点の変化(スピードの経済)
80年代の仕組みは良かったが、条件が変わったので合わなくなった、と通常言われるが、仕組みの問題と条件の変化というのは一緒に論じると議論が混乱する。
ex.
NECのパソコン事業が挫折したのは、電電ファミリーの一員で管理が肥大したシステムであったからである、といわれるが、これではいったんは世界を制覇したことを説明できない。管理から脱却する努力はなされていたし、ジャストシステムと共同で日本語ワープロの開発という画期的な技術革新を達成した。しかしDOS/Vの開発で日本語の壁が消えてしまい、ウィンドウズが急速に世界に広がり、競争条件が変わったことによって、システムそのものは悪いわけではないが敗北した。
仕組みでなく条件の変化こそが問題であるという面もある。
1990年代の歴史的位相
今回のプロジェクトでは、一つのシェーマで括ることはせず、対象を共通にし、今までの自分のディシプリンをはっきりさせてこの対象にぶつける。
私自身の宇野経済学でいうと、全体研究『福祉国家』と『現代日本社会』の際、加藤栄一氏が、資本主義の純粋化傾向からそれが反転して福祉国家化へ向かう、というように、段階論の再構築を試みた。90年代は段階を画する、再び純粋化へと向かう再逆転と考えた方がよいのかどうか。
また、馬場宏二氏は、基軸経済国という概念を使い、『現代日本社会』では、それがアメリカから日本へシフトした、という認識があった。しかしこれは90年代の現実からするとずれている。これをどう考えるか。
これらがとりあえず私の対象への入り口となるだろう。
<記録:土田とも子>
|