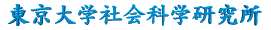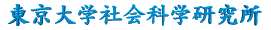II
次に今の日本の原子力の現状を考える時に、原子力はエネルギー安全保障上はずせないと言われる。その定義は、日本は輸入エネルギーに依存しているので、国内に核燃料サイクルを確立することによって、エネルギーを自国でまかなうというエネルギー政策の基本としての意思決定をさす。
60年代のこの意思決定が、しかしその後実際には思うようにいっていないのは、核燃料サイクルは予想以上に膨大な投資を必要とするものであること、また世界中のどこかで事故があってもすべてに影響を受けることがあげられる。また技術的には国産といえても、世界社会情勢にいつも左右されるため、必ずしも国内にあるというだけで完璧に保障できるものではない。基本的にはこの意思決定は変わっていないのだが、どういう道筋で変化してきたのか、日本における原子力の歴史について振り返ってみる。
40年代、日本に原爆が投下された直後、アメリカは世界の原子力の技術を禁止しコントロール下におこうとした。また国際原子力規制機関を作ろうと提案をし、独占を図ったが、実際には原子力の平和利用を推進する事によってアメリカの技術を提供しながら、2国間協定を作りアメリカのコントロールの元に置こうとした。また国際原子力機関を作ることによって民生用利用の軍事転用を監視しようとした。その後原子力研究の禁止を事実上取り除いたアイゼンハワー大統領による歴史的国連演説「アトムズ・フォー・ピース」(1953年)に日本の原子力開発の歴史が始まったと言える。政府と学会との間に激しい政治闘争が生まれたが,学会の意向で自主,民生、公開を規定している平和利用3原則が盛り込まれた。
原子力基本法が1955年が成立し、56年に原子力委員会が発足した。世界的にこの動きは横一列に並ぶ。同じ56年に「原子力の研究,開発及び利用に関する長期計画」(長計)が策定される。この1956年の長計をみると現在の原子力政策の原点が以下のように明記されている。
「。。。使用済みの燃料の再処理についてはできる限り国内で行うこと。。。核燃料資源の有効利用という観点から、高速増殖炉(FBR)が我が国にとって最も適した原子炉であり、その開発を我が国原子力開発の目標とする。」
これは、当時ウラン資源が希少資源と考えられており、FBRの開発が不可欠という世界の原子力開発計画の潮流にならったものであった。(FBR:ウランを原子炉で中性子に当てて出来るプルトニウムを回収してみずから増殖していく)
しかし10年後、アメリカ、ロシアのFBRの開発はなかなかうまくいかず、その間に軽水炉(水、濃縮ウラン使用、潜水艦用の小型原子炉を改良)がアメリカで生産された。世界的にこの軽水炉路線が商業ペースに乗り拡がり、日本もこの軽水炉を導入する。しかし学会の意向で自主,民生、公開を規定したにもかかわらず、その直後に軽水炉の技術が導入されたことは矛盾を生んだ。このため、本意ではないと言う理由で最初の原子力委員会の委員である湯川秀樹が辞任をする。
経済的に早く原子力を導入したい産業界と確実に自主技術で進めていこうという国の意向が食い違ってきている。
現実にはその後、軽水炉計画はどんどん広がり、67年には今後20年間は軽水炉を使用する方針がうちだされた。当時ウランはまだ希少資源という観点から、その後のFBRの導入の準備段階として、実験炉→原型炉:もんじゅ→実証炉(80年後半予定)→商業炉という4段階の開発計画をたてた。67年には動燃事業団を作り、全部で30年位の計画でFBRの核燃料サイクルの達成する予定をたてた。
FBRでは軽水炉から出る使用済み燃料の中に含まれる1%のプルトニウムを取り出す、つまり再処理が必要になる。動燃はその再処理施設を商業施設として作ってしまった。軽水炉は商業施設、そこから取り出す使用済み燃料も商業施設に属し、そこからプルトニウムを取り出す技術も商業施設に属すると大蔵省は見なした。そのため東海村の再処理工場は研究所ではなく営業目的の事業所とされている。一方そこでの技術は、フランスの技術導入によって始められることになり、国内技術で行うという目標に反することになってしまった。
<記録:中島美鈴>
|