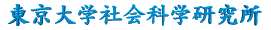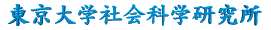|
【大瀧 雅之】 90年代の日本経済とマクロ経済学:市場と組織—相互補完的な秩序—
I.はじめに
これまでのマクロ経済学は貧困なものであった。というのも経済現象の評価(雇用や景気、インフレ、デフレなど)が、マクロ経済学と称する学者の恣意に委ねられていたからである。
その反省の上に立って出てきたのが、いわゆるパレート・エフィシャンシーという考え方であり、それは、俗に言われてような、近代経済学は効率重視で血も涙もないといった見方とは違って、非常に広く、深い概念である。このパレート・エフィシャンシーという概念を使って経済現象を評価していこうというのが新しいマクロ経済学の立場であり、パレート・エフィシャンシーという概念から物事をみるということは、何を意味しているかというと、まず消費者主権ということであり、普通の人々の幸福をいかに増進させるかということが近代経済学の関心・目的である。この目的のためには、家計および企業の経済活動の描写が不可欠になってくる。そこではどういうアクシオムで描写がなされるかというと、経済合理性という概念(すべての人間の経済行動が合理的にとらえられるということではなくて、ひとつのアプロクシメーションとして十分意味を持つということ)である。ただしそれはあくまでも経済学のファースト・ステップに過ぎない。最終的な目的は、家計・企業・政府などのあらゆる経済主体の相互作用が働く場、経済学でいう市場のパフォーマンスを評価することが究極的な目的である。
その際、経済学は基本的に二つの流れからなっていると考えることが自然であり、ひとつはスミスに端を発する古典派的な考え方であり、もうひとつはケインズ的な考え方である。前者について、現在の経済学のタームでは、厚生経済学の基本定理と呼ばれ、スミスの「見えざる手」を数理的な言語を使って表現したものであり、この基本定理が成り立つ場合、市場というのは非常にエフィシャントなメカニズムになり、パレート・エフィシャンシーという考え方からみて全く無駄のない配分を達成することを可能にすることになる。すなわち家計や企業などの経済主体は私的な欲望に基づいて行動するが、しかし意図せざる帰結としてマクロ的には効率の高い無駄の無い社会が現出するというわけである。おおかたの場合において厚生経済学の基本定理が成り立っていると考えるのが、ネオクラシカル、新古典派マクロ経済学と呼ばれる流れである。そうではなくて市場のメカニズムには限界があり、「市場の失敗」を重要なファクターとしてみなし、市場は自己完結的ではなく何らかの外的要因に支えられなければならないというのがケインズ経済学の考え方になる。私の思想的な立場は、ケインズ経済学寄りであるが、ケインズ経済学にも非常にまずいところがある。市場が自己完結的な組織ではあり得ないという点では、私はケインズ経済学の支持者であり、市場を補正するような何らかの外的な組織が不可避的には必要であるとは考えるが、しかしそのような組織がそれ自身でうまくいくのかという問題もある。つまり市場に対比されるものとして組織があるが、その最たるものは政府である。ケインズ経済学にはHarvey Roadの前提というものがあって、(私はこの考え方は気に入らないが)政府というものが効率的な無私なエリートによって支えられ、エリートの規律によって保たれるというのが前提としてある。ケインズ経済学の最も大きな問題は、市場の機能が自己完結的ではないことを認めている意味ではレラバントだが、しかし市場と補完的な組織である政府に対して無限定的に肯定的だということである。80年代から90年代に起きた日本の企業や役所のスキャンダルについては、原因は市場のほうにあるよりは、むしろ組織の規律付けにある。ケインズ経済学は、「市場の失敗」については注意深いが、「政府の失敗」については過度に楽天的である。その際、新古典派を自分の思想にするのか、ケインズ経済学を自分の思想にするのかというダイコトノミーは、むしろ危険なものの考え方であり、不毛なイデオロギー論争に落ち込んでしまうと私は思う。
<記録:渋谷謙次郎>
|