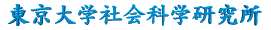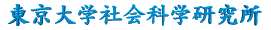|
【平島 健司・中村 民雄】 第9回プロジェクト・セミナ
討論要旨
質問
現在、国際的な資本の移動のもと、通貨統合の過程で為替レートを安定させることができなくなった結果、大陸ヨーロッパや北欧で従来のケインジアン的経済運営ができなく名的他といわれている。今、オランダの奇跡といわれているが、80年代には国際資本移動の結果、オランダやベルギーは調整が迫られ、失業率が高い国であった。この時はスウェーデンは経済パフォーマンスがいい国だったが、現在は資本の自由化を余儀なくされスウェーデンモデルの変容が迫られてきた。ドイツの場合、ヨーロッパのアンカー・カ レンシーで、中央銀行の独立性ゆえにインフレ率も低いため、そうした改革というのはどのくらい必要であったのか疑問が残る。他の国だったら、為替レート安定のための国内ディスインフレ政策が必要であるが、平島氏の言ったドイツの国内的な改革が限定的ではなかったかということの理由は、国内政治的な問題なのか、それとも国際的な通貨統合の中のドイツの位置に依存するのか。また、国際化にともなうドイツの国内改革の必要性はどのくらいあったのか。それと関連して、変化の要因が、ヨーロッパ 統合なのかドイツ統一なのか。日本とのアナロジーで言えば、国際化なのか 国内の不況なのかの疑問が湧く。ドイツの統合に伴う変化がどのくらいかということについては平島氏は疑問符を付している。(つまり「ドイツモデルが崩壊している のか?」と)。ドイツ統一による財政問題が重大であったとすると、財政問題に端を発した改革の方向はどちらにいくのか。ネオ・リベラルな方向に行くのか、 ヨーロッパ統合なんだからドイツだけが特有ではなくてヨーロッパが同じ方 向に行くのか、それともドイツが独自の制度をもって独自の方向に行くのか、お聞きしたい。
平島
私の議論は、80年代から90年代を歴史的に俯瞰するものであったが、そこで注意すべきなのは、幸か不幸か欧州統合の進展と国家統一とがリンクして進展した点である。ご指摘のように、ドイツの中央銀行は、70年代以降に新しい政策理念を推し進める国内政治の主体として重要な存在であった。連邦銀行は、統一後の政策を変化させる上でも重要な役割を果たした。したがって、その存在自体や通貨にからんで問題が政治化することはなかった。その意味で、通貨統合に対応してマクロ経済を調整しなければならなかった他の国々に比べてドイツは余裕があった、といえる。しかし、他方では、国家統一を達成しなければならなかったために、財政的負担は急激に膨張した。例えば、シュトレーク(Wolfgang Streeck)は、伝統的なドイツ・モデルでは、ドイツの産業はもはや対外的競争力を維持しえない、という議論を展開しているが、そこでは通貨の問題は表面に出てこない。つまり、ドイツにおいて、第3次産業に新しい雇用を創出しえないのは、労働組合や団体交渉の硬直的な枠組みにこそ問題があると考えられている。そこでは、金融政策や通貨統合の要素はすでに織り込み済みであり、議論の前面に出てこない。私も、このような議論を前提としたから、金融、通貨問題については十分な注意を払わなかったのかもしれない。しかし、ドイツ・モデルの危機が、80年代以降の対外的問題(通貨統合)によるものか、それとも急激な国家統一によるものなのか、について単純には答えられない。
質問
ヨーロッパ法をイギリスが受け入れていく中で保守党から労働への政権交代をどのようにとらえているのか。連続性という筋でよいのか、それとも何らかの断絶があるのか。あるいは労働党政権が成立して日が浅いので判断は難しいのか。
中村(民)
それは分野ごとに違うとしか言いようがない。ほとんど変化がない部分というのは域内市場統合についての価値観である。大きく違っていたのは社会政策である。48時間労働指令の成立をしつこく阻止しようとしていた保守党に対して、労働党政権は、政権に返り咲くやいなやマーストリヒト条約で積み残しになっていた社会保障、社会政策の先進的な規定を全部採用することになり、48時間指令への改定交渉の席にも就く、というように、分野によって違いがある。私は立法面での連続・非連続にはほとんど触れず、判例法による条約の解釈の影響力が連続して起こっている方を強調して話したので、少し説明にアンバランスであったのではないかとは思う。
質問
大陸法をイメージしたような行政法のシステムのようなものはイギリスの場合は伝統的にはなく、細かい部分では適用しているということだったが、大陸法的なところではそれなりにかっちりと出来上がった行政法の体系があり、その法を適用して行政がなされているというイメージをもつ。そうしたイメージをもったうえで先ほどのCitizen's Charterなりを用いて行政を別の角度からコントロールするという形で考える場合と、そうした前提が違う場合とでは理解のしかたが違ってくる。その前提はイギリスではどうだったのか。また、先ほどお話になった分権化の問題はスコットランドやウェールズ、大きな単位の州の自治で、それより下の地方行政の単位も変わっているのか。そのこととの関連で行政改革は中央省庁のレベルなのか、地方政府レベル、あるいは末端の自治体レベルでの話なのか。さらに、行政と市民との関係で今のような話をしていくと企業と行政の関係はどうなっているのか。
中村(民)
コモン・ローの世界でも行政法の基本原則はあった。権限踰越(ゆえつ)の統制、あるいは適正な手続の原則などがそれである。ただしフランスやドイツのように、行政裁判所といった制度的機構やそれにともなう行政法体系をつくり、私人間の法律体系である民法などと別個の法体系・裁判制度までを作ってしまうということまではやっていなかった。大陸行政法と重なり合うところでは、例えば裁量権が逸脱しているのか逸脱していないのかについての審査基準やその基準をとるときの実質的な根拠づけなどは大陸法とそれほど違わない。大陸行政法とかなり異なるのは、イギリスでは非法律的な手法や効率性などの価値観によって統制していく考え方が比較的多く出てきている点である。次に、地方分権については、ウェールズやスコットランド内部のさらなる下位区域をも変えていくのではない。ウェールズやスコットランド単位、そのレベルの分権が論じられている。ただし、ロンドン市は別である。ロンドン市だけは首都ということで、そこの市長・市議会に自治権をある程度与えようというのが今次の立法であった。また、行政改革の中央と地方との区別の問題については、基本的には中央で行われることは、すべて地方にもあてはまる。企業に位置付けについては、日本の規制緩和の流れと同じである。 質問
ウェールズやスコットランドという単位の分権に際して、EUレベルでの国境を越えた州単位の自治の流れのインパクトが与えた影響ということはあるのか。スペインやイタリアは、大きいレベルでの分権を行って直接お金が流れてくるが、フランスでは州の規模が小さくてそうしたことはやりずらいが、いくつか合併してEUレベルでの自治を実現していこうという考えもある。
中村(民)
イギリスの場合、国内での分権は1950年代からの流れがあるが、それがたまたまEUの発展と重なったところがある。ご指摘のとおり、地域的には隣接関係になくても利益的には共通点がある自治体同士が連携してEUからの補助金である「構造基金」をもってくる例は多々ある。例えば斜陽産業を抱えている各国の都市同士が国境を越えて組んでブルッセルでロビーイングをすることもある。これらの動きから分かるように、一国内でいえば、イングランド、スコットランド、ウェールズそれぞれにある類似問題を抱える自治体同士の連合体とEUとの関係、あるいは各国の類似都市同士の連合体とEUとの関係といったような、地方的国際関係といった独自の世界が出てくる。要するに、地方分権とEUのお金の流れというのは、ある程度重なる。しかし、それだけではなく、前史もある。
質問
中村氏の行政改革の議論で、行政改革が全体として何をねらいにしているのかとうことと関連してくるが、第一段階の88年のThe Next StepとCitizen's Charterのところをみていると、行政に金がかかって公務員が働かないというので、スリムにしてもっと働かせようという「経済三兄弟」の理屈があるわけだが、Citizen's Charterは「シティズン」と言っているので、別の筋があるのではないか。つまり国家に寄りかかっている人々に対して国家に寄りかかってはいけないという新しい路線を出したときに、マーケットメカニズムを一方で強調して公行政の中にも経済の論理を貫徹させるという論理がある一方で、もう少し市民の可能性を上手く使うという考えもあるのだろうか。キーワードで言うと、市場と市民社会の論理のように。
中村(民)
基本的にはCitizen's Charterは「経済三兄弟」の道具として使われている。従って労働党政権の下ではもうCitizen's Charterという言い方はしなくなって、「サービス・ファースト」といった言い方がなされている。
質問
しかし、いまの市民の可能性という点は、「ソフト・ロー」という、国家的な強制力を背景にしないが、しかしルールとして一定の拘束力をもつという場合、そうした拘束力はいったいどこに依拠するのかという問題にも関連するので "Law and Economics"の論理と「ソフト・ロー」の論理があるという話になれば全体像としては、ひとつの筋が立つのではないか。日本との比較でいうと、主婦の人たちがNPOを利用して育児の連帯的組織をつくって、他方でそこで集めた情報を生かしてスモール・ビジネスをつくるということ報道されていたが、色々な新しい可能性が出てきているときをみるときに、上記の二つの視点があり、イギリスに関してもそのような視点をみることができるのではないかと思った。
中村(民)
なるほど。
質問
ドイツのシュレーダは、「ドイツのブレア」を標榜して登場したが、両者がヨーロッパの社会民主主義を打ち出した。その結果EC議会の選挙で負けたが、全体としてヨーロッパの統合の中でヨーロッパの社会民主主義がそれぞれのモデルを探している。独英は互いにどのようににらみながらやっていくのか。もっともそれ自体が独自の課題なわけだが。
平島
先ほどの私への質問とも関わってくるが、ドイツは、通貨統合を推進する上でも、また予期せぬ国家統一に対しても、80年代に進めた財政再建という実績を糧とすることができた、という点である。しかし、後者については、旧東独の実態を完全に見誤ったために、大きな財政負担を抱えてしまった。その結果、減税と歳出削減をきわどいバランスをとりながら進めざるを得なくなった。このような緊縮政策は、労使関係にも影響を及ぼす。すなわち、対外的競争力を回復するために、社会保険の一部を負担する企業の負担をこれ以上は増加させない一方、もっぱら投資優遇的に税制改革を進める、という方向が出てくる。しかし、ドイツでは、政府が一方的にこれを推進することができないから、「雇用のための同盟」というようにコーポラティズム的な協議が設定された。ただ、通貨統合に伴う財政規律の条件は、政府が、歳出増を求める主張に抗して緊縮を進める上では格好の政治的理由となっている。
質問
ヨーロッパの社会民主主義政権の改革路線の中でグローバル対応のところと、従来の構造に規定されたナショナルなものの対応の違いが出てくるのではないかと思うが。特に現在、司法改革と大学改革に関心があって、ドイツの大学改革などは、もっぱらアングロ・サクソンの用語を使ってやっているわけだが、いちばん文化と関係するところでもあって、なかなかうまくいかない。なぜそういうような改革をせまられていくのかということが課題として認識され、しかもそれぞれナショナルな条件に規定されて独特の改革政策をしていることになるのだろうが、独英の話をするとき、共通のベースがあって、独英の偏差もある。それが日本との比較でいうとどうなるのか。もう一枚かませてやるとおもしろいと思う。
質問
>中村(民)氏のいうCitizen's Charterというのは、今日本で進んでいることとの比較でいえばCitizenという言葉を掲げただけのものがあるのではないか。日本の省庁では色々な再編が行われていて、それぞれの省によって意見が違っていて混沌としているが、自己評価とか第三者評価ということを言っていても、苦情処理という形で利用者側の評価を組み込んでいくというところが弱いという気がする。だからイギリスは、そういう意味では、今日本で夢中に議論されていることよりもましなのではないかと思う(笑)。
中村(民)
そういう意味では、その通りである。利用者の評価という観点が日本になさすぎると私も思う。ただ、私がさきほどの質疑応答で、Citizen's CharterのCitizenにあまり強い意味がないと評価していたのは、イギリスにおいて行政と市民という対抗関係のパラダイムが崩れるくらいの参加型の行政がCitizen's Charterから生じているのかという観点から見ていたからだった。その観点からすれば、苦情処理もなるほど市民からの評価だが、所詮、事が起こった後になされるものであって、裁判で事を解決する従来の態度とさほど変わらないと見える。むしろ、税金の効率活用といえる行政サービスかどうかの判断基準を設定する段階、つまり事が起きる前の、事前の行政手続段階に市民が踏み込むのを認めてこそ、対抗のパラダイムは崩れ、市民参加の、市民本位の行政という構図になる。しかし、その点では保守党政権のCitizen's Charterはそこまでは踏み込んでいなかった。
<文責:渋谷謙次郎>
|