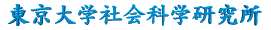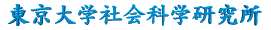討論要旨
司会
増山氏は、山口氏の分類によると入力システム自体に注目した場合、政権交代はなくても変化はあり得る、という報告であった。お二人の話はやや局面が違っている。
質問者A
今回のプロジェクトの柱になっているのだが、政治改革後さまざまな政権交代があった。そのことと、橋本行革と地方分権改革が実際にアジェンダにのぼってきたこととの関係を、山口氏はどう見られたか。もしこの時期政治改革問題がなく自民党の力がそのまま続いた場合橋本行革や地方分権改革はあり得たか。
山口
自民党にとって1年足らずでも野党を経験したことは大きい。官僚との距離感をはじめて自覚した。官僚へのフラストレーション、自分たちが責任をとれる、指導力を発揮できるポジションでは無いというフラストレーションは自民党の中にもたまっている。政権交代が無ければ行革という発想は出てこなかったとは思う。地方分権改革も、自・社・さ連合政権の実現がなければああいう形ではあり得なかった。当時の村山政権下の閣僚の配置なり、地方分権改革に対する指導力を発揮する仕組みが分権推進法の立法や分権推進の立ち上げに力があったということは確かである。政権交代が全く不毛だったとは思っていない。NPOとか情報公開法とか、従来の55年体制の延長では出てこなかったような政策が90年代に実現した。初期の自・社政権時は、たとえば加藤政調会長は自民党の支持基盤もmodernizeしていかなくてはならないという問題意識を持っていたし、社会党等も連携して新しい市民社会という考えのもとに新しいタイプのイシューを取り上げていった。これらは従来の自民党単独政権では実現できない政策であった。
質問者A
自民党内の官僚制へのフラストレーションがあり、それについて何も有意義な解決が付いていない。何がネックになっているのか。
山口
一つは公共事業だと思う。公共事業については農水省、建設省担当官庁で大きな予算を持っている。こうした資源を自分の選挙区に引き出すことが、政治家としての活動の非常に大きな比重を占めている。その中では集権体制や官僚支配や補助金体制を問題にすること自体が見当はずれのようになってしまう。むしろ橋本政権末期以降、景気対策で従来にまして大盤振る舞いをするなど、古いスタイルの利益誘導型のビヘイビアに拍車がかかってしまった。大半の自民党政治家にとって、官僚主導でもかまわない、事業を持ってきて支持基盤が強化できればよい、ということなってしまう。選挙の心配のない政治家が最も官僚批判をする、という構図がある。
司会
増山氏と山口氏の話の関連について。イギリスの例を出されたが、サッチャー政権による大きな変化は80年代であった。80年代のイギリスがおかれた状況は少なくとも経済的には大きな違いがあるので比べることは出来ないかもしれないが、80年代まで含めて考えたら日本の変化ははたして十分なものか、そうでないのか。
素朴な印象では、日本の政治はあまり変わっていない。変わる必要がないから変わってないのか、それとも変化する必要があるのに変わっていないのか。社会の次元で、政治に変化をもたらさざるを得ないような大きな変化があるのかないのか。
山口
イギリスと日本の違いは大きい。イギリスの場合労働組合や左翼勢力の力が大きくて、それがもたらした弊害が大きくなって行き着くところまで行き着いた。当時の国内における左右の政治的対立の局面の中で、サッチャリズムは一度大きく右にふれた。左翼勢力の権力的基盤に相当くさびを打ち込んで、政治社会がかなり変わり、いわば旧左翼を地上げした後にニューレイバーが出てきて、中道左派的なところでサッチャーに揺り戻しをかけて政権を作った、という構図である。こうした国内の権力構造の振り子の中で大きな再編が起こり、その後グローバリゼーションで政策の転換が進んでいった。
日本は80年代に今までの体制では立ちゆかなくなるといわれてはいたが、切実に国内の政治の要因で、政治力学として反対側に振れて改革をしていくようなことはなく、行革、小出しの規制緩和・民営化等々、微調整的に変わっていった。80年代後半〜90年代に本格的なグローバリゼーションのインパクトがあり、外との関係で政策転換を語らなくてはならないという構図があった。国内の政治的対立がうまく整理されない中で外からの課題に対応しなくてはならない。グローバリゼーションへの対応派とドメスティック派とは、どの政党の中にもある。
増山
選挙によって政党の趨勢を見ると、戦後ずっと保守党と社会党の対立図式があり、その中である時期から、保守政権が弱くなっていく傾向と野党が多党化していく傾向という二つが趨勢としてあった。80年代は、自民党がなんとか単独政権をとることが出来、90年代は一つの政党が単独で政権をとれない時代になった。政治的にダイナミックな状況を、選挙が作っている。
質問者A
増山氏のいわれる政党の流動化が起きたということに関しては、山口氏との間に不一致がないが、山口氏は、現実には入力過程が細ってしまい、出力も影響されて新しい入力がないという事態が述べられた。この編集計画では何人かの執筆予定者が90年代に入力に何らかの変化があった、と見ているようだが、その際に山口氏の話と違った切り口が出るのだろうか。
増山
住民運動・NGO等との関係などの新しい動きについては、山口氏も述べておられる。流動化したり混乱している政党の選挙運動の戦略の変化なども見られると思う。こういう状況の中で政党の行動がどうなったかを明らかにしようというもくろみである。
質問者B
山口氏に質問したい。
小選挙区制の導入を肯定的に主張する文脈として、
- 小沢の新自由主義的改革→利益誘導政治を変えなくてはならない→自民党自体の改革→選挙制度を変える、という、路線政策があってそれを実行する手段として制度を変えていこうとする——政策・路線アプローチ
- 二大政党制の方向へ結びつけ、政権交代を実現すること自体を期待した改革——統治システムアプローチ、の二つがあったと思う。
この両者の関係を、政治学はどう考えてきたのか。
たとえば大嶽秀夫氏は、橋本行革も政権流動化以降の対立軸の混乱も、分析の足場を路線におく、1の立場で考えている。そういう考え方と、今日の報告のように、入力・変換・出力というところから見てどこに問題があるのか、と考えていくやり方とが、うまくかみ合ってないのではないか。
なぜ改革の結果のシミュレーション分析をしないかというと、ある制度を改革するについて制度それ自体の変化を過大評価して、どういう人々が何のためにそれをしようとしているのかを見なかったところに問題があったのではないか。
山口
自民党内でもリクルート事件等に関連して、抜本的な改革が必要であるとの危機感を持っていたが、この”抜本的”というのはすぐに選挙制度改革につながる思考回路がまずあった。あらゆる問題を政治家は自分たちの最大の関心事である選挙に結びつけて考える傾向があったこと、政治家の経験として、選挙にエネルギーがいりすぎる、特に中選挙区は同じ党同士で競争が激化しすぎる、これを変えなくては、という考えが以前からあったことなどによる。
これらから改革派が自民党内で称賛を浴びるようになっていった。
政策転換が進まないとか、政党間で明確な対立軸を持って論争していくとか、健全なビジョンが出されない、というような日本政治の問題点について、選挙政治というファクターがどう絡んでいるのか、つまり選挙制度と政党政治の機能不全との関連が分析されなかった。
政党政治がそれ自体で完結しないのが日本の特徴である。90年代の政党政治については、政治家の言説をそのまま額面通り聞くことのばかばかしさを感じる。選挙で勝つとか政党組織を統合していくために何が一番必要かという場合、政党の立脚基盤ということになる。
55年体制の時代は、政治化した労組が左翼政党のスポンサーになり、政党の基盤になっていたが、80年代連合などができてそれがなくなり、対抗勢力へのサポートがないという構図になっていた。小選挙区制にすれば二大政党になるという議論は、野党になっても政党が求心力を保てるという前提が無くては成り立たない。イギリスの場合は長く野党議員をやっていてもそれを支えるインフラがある。90年代に明らかになっていったのは、日本は与党にならないとそれがないということである。政党や政治家の活動を支えるものがどこにあるかを突き詰めて考えた上で、二大政党論を追求すべきであった。
質問者C
ブレアはconstitutional reform よりは、改革のシンボルとしてはmodernization のほうを意識的に使っていた。イギリスの場合中央・地方の関係の改革は、スコットランドやウェールズとロンドンの分権の位置づけなどについても、きちんと考えたものではなくその場その場での党利党略の絡んだものである。上院を地方代表になどという考えは全くないなど、ドロナワ的なものにすぎなかった。
また、日本の行政改革について言えば、それは橋本行革で始まったわけではなく、NPO法案や情報公開などについての検討、政治改革と行政改革は車の両輪、といわれるなどその取り組みは細川内閣の時にはじまった。その言葉・シンボルが中曽根行革にハイジャックされ、公務員の数を減らす、ということに矮小化されていってしまった。
政治改革についていえば、改革を担う側のシンボルのマネジメントがなっていない。それも政治改革が選挙制度改革になってしまった一因である。行革も意味がすり替わっていく。浮動票が多くなって選挙競争が厳しくなっている中で、改革派はメディアにこれほど注意を払わないことが不思議である。
山口
イギリス労働党どこまでまじめに改革をやったかという問題はある。
スコットランドの問題の場合は、グラスルーツで出てきたアイディアを労働党がピックアップしたというところがある。その後の具体的な運用になると混乱・葛藤が起こっていることは確かである。制度改革をどこまで詰めて考えているか、ということが重要で、日本の場合はきちんとした備えが出来ていなかった。政治学者は政権交代を予想していなかった。
行革の話。たしかに細川政権の時に官僚機構の持つ権限そのものに切り込んで、透明化するとか分権化するなどの問題意識があった。しかし改革の手順として、選挙制度改革をまず片づけないと先へ進まないという考えがあったようだ。そのあとの本来の改革の話はかすんでいき、細川氏の政権も細っていった。
質問者D
日本政治と政治学の挫折、という問題だが、政治学としてなぜこういうことが起こり、どこが悪かったのか。再出発はどこから出来るのか。
政治改革を選挙制度改革に矮小化したことへの批判は当時からあちこちで言われていたのに、にもかかわらずたくさんの政治学者がそれに熱中した。その根拠は、改革の主体に注目し、自己改革の原動力、自己改革の駆動力を選挙制度に求めたからではないか。これが挫折したのはどこに間違いがあったのか。小選挙区比例代表制という制度が悪かったのか、政治の自己改革の可能性を政権交代に期待したのが悪かったのか?自己改革能力に着目したことそのものが悪かったのか?
山口
政治学の責任ということでいえば、制度設計に向き合わなかったのが悪かったと思う。92年の政治学会で「選挙制度改革」というテーマが出たが、選挙制度を変えることがどういう帰結をもたらすかについてほとんど議論の蓄積がなかった。個別の国の例に関する知識はあっても、日本の政治の文脈を押さえた上で、ある制度の導入をしたらどうなるかという議論がなかった。これは改革に関与した政治学者の怠慢であった。
成功した改革といわれる地方分権改革に関わった政治学者も、機関委任事務の廃止の方向を決めて各省官僚と議論して初めて、機関委任事務とは何かをよく理解した、と言われる。政治学者は制度の実態、運用など現実との向き合い方が欠如している。
主体の自己改革から手をつけるか、環境要因から変えるか、という問題はかなりのちにならないとわからない、という面もある。
質問者D
日本の政治学への提言としては、もう少し個別の論点を詰めていくことから積み上げるべきであるということか。
山口
少なくとも改革に関わる人々は制度設計を詰めて考えるべきである。
質問者A
93年〜94年 イタリアやニュージーランドも選挙制度改革を実施した。ニュージーランドは学問的に詰めた議論をし、様々な制度の得失を勘案し、ランキングを行い、質の高いレポートをまとめて準備したが、しかしそれをやっても結果は満足できるものではなかった。それまでのニュージーランドの政治についての不満を背景に考えないと、良い結果は生まれない。
要するに学問的にシステムを設計してもあまり効果はない。選挙制度改革をやったところはどこもその後改革の再検討をやっている。学者の仕事としては現実政治に対するものはその程度なのかもしれない。背景と改革の意味を大きな文脈の中で考えないと、理論的な選択は背景に影響されてしまう。
質問者E
制度改革の評価について伺いたい。地方分権改革が唯一の成功した改革とまとめられていたが、大きな改革の試みとして大蔵省の改革・再編がある。この結果大蔵行政の変化についての評価はどうか。
山口
金融監督庁を分離したのが大きな意味がある。金融の世界の大きな変化を反映して、本来の監督能力を持つ機関を備え、そこでスペシャリストを育てるという点では重要な改革であったと思う。
質問者F
結構変わったのではないかというのが私の印象である。経済構造改革は、やっている自民党自体は変わらないが、大胆な規制緩和を実施するなどの変化がある。大店法は選挙基盤の商店主を切り崩すことになって今になって困っている。外圧もあるだろうが、規制緩和は大きな変化だった。なぜあれだけの規模の規制緩和が行われたのか、政治家自身のかわらなさとの落差で不思議な気がする。
山口
政策の内容面はいろいろな変化が進んでいる。90年代、グローバリゼーションへの対応の中で、業界、与党、官庁の関係が変わったのは事実だ。
しかしこの中で政党は理念的な選択の上で改革していっているわけではない。一方で規制緩和はせざるを得ず、市場化を進めるが、規制緩和で打撃を受ける人々を補助金でケアするなどの場面で政治家は一番働ける、という面もある。グローバリゼーションの中で相反する政策は多い。その方向性は自民党自身にも見えていない。橋本政権は方向性を持とうとした形跡があるが、小渕政権以降特にこういうことが目立つ。
司会
政党政治を通じないで、後から見ると大きな変化が経済・社会の中に生じている。つまり選択がなされない間に変化が起きるから、政治の機能不全ということになっているのではないか。連続性がある、ということであったが、そうであれば官僚は社会の変化をきっちり見た上で改革しようとしているのか。
山口
通産省、運輸省が変わっていることは確かである。従来のような業界保護行政ではもうやっていけないという認識はあり、官僚自身の自発的な改革はあると思われる。
質問者A
行政改革委員会の委員だった人の話を聞いたが、政治家は規制緩和に関しても、行革に関しても委員会をつくること自体が重要であった。作って、その後の過程では規制緩和推進、行革推進に反対したりする。推進は経団連などが熱心に進めた。政治家は最初と最後だけに登場する。
政党が変わらなくても変化が起きる。
しかし政権交代がなかったらこれらがアジェンダに載ったかどうかわからない。
質問者G
帰結のシミュレーションがない、というはなしだが、法律制度の制定過程などを見ても、最近官僚は改革しようとはしていても、その中身を詰めずにいい加減な理由付けでやっているように見える。かつてはなかったようなことが90年代に入ってから目立つ。
平成11年版の厚生白書の社会保障経費についての箇所もずさんなデータ・議論である。最近官僚の質が変わってきたのか。これは政治家の動きと似ているか。
社会保障費の負担増の問題、これでは持たないので制度改革しなければならない、という路線を出すとそこに集中してしまい、自らの主張を論証するためには何でも持ってきて強引に主張する。マスコミもそこに乗り、反対論が起こりにくい構造になっている。行革、選挙制度改革についても同様であった。
ここまで年金制度に対する不信感を醸成して、これからそのツケがひびいてくるだろう。フランスでも年金財政について同じような問題が起こったが、かなり対応が違う。一方で負担増をどうするかの議論があり、もう一方でこれは1946年以来の国と労働者の契約であるからそれを反故にすることは出来ないという議論があり、その中間で具体的にどういう対応をするかが政府レベルで議論された。マスコミの対応のちがいも関連する。
もう一つ、国土建設交通省という行政改革の方向を見ると、建設・運輸・国土庁は何も失わず膨大な資金・権限をにぎることになる。分権化も入ってはいるが地方も国もコントロールできないところに膨大な資金の裁量配分が行く仕組みを作っている。分権改革を評価されていたが、こうした実態に即した評価をどう考えるかという問題がある。
国土建設交通省は作るがその使途は地方で決める、といっているがおそらく実態は分権にはならない。それどころか国が都市政策をどうコントロールするかという議論も出る。
都市は国家の財産である、だから公益的な観点から政策を立てその中核は国が握る、という議論も出ている。
山口
官僚の資質、責任感という問題について。財政投融資にからむ不良資産や債務の問題についてはある種の判断停止状態で責任回避が目立つ。
社会保障の将来像についても明確なビジョンがなく場当たり的。
改革の論争における一方的な進め方—別の議論が出にくく意見の多様性がない状況の中で方向づけが決まる、という状態は日本の政治に昔からあった。価値判断に関わること、たとえば負担率50%を超えてはいけないとか、消費税の際の直間比率を変える必要があるとかのことを審議会がまず出し、そこへ向けて走るようなことは今までにもあった。
その審議会の価値判断は行政がかなり主導しているしマスメディアもそこに乗る。
省庁再編成の中身の評価については、やはり国土交通省などを見ると危惧がある。
重要な改革を進めるとき、たとえば選挙制度改革などについても審議会は重要な方向づけをするものであった。そこにある種の立場にある人が審議会の委員になり、マスコミの代表なども入るので、異論が出にくい構造になる。
<文責:土田とも子>
|