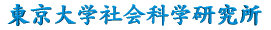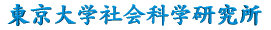|
―― 議論 ――
○ 90年代の国際的な不況の中で、企業単位の変化、国民経済の変化だけでなく、産業構造がどう変化したかも重要で、これは前回の大滝氏のブレゼンテイションでも、今回の橘川氏の話でもはっきり分からない。政府が市場を見るとき、産業のウエイトや配置、産業間の関係がどう変化しているかということを見る。これが出ると政治学のほうではやりやすい。政治学をやっている側から見ると、企業そのものが国際化、多国籍化することによって、制度の改革が必要になり、他の産業へも影響を与える。国際的にも産業構造の変化があり、これも国内の変化にはねかえる。90年代の変化を見るときこの面は重要である。
○ 橘川氏のVの政府・企業間関係は規制緩和など個別の政策、対策に特化されている。今の国際的な産業構造の変化がもたらすインパクトという話になると、通産省関係だけでなく郵政省の守備範囲、情報など、も、広く関わってくる。こうしたことをどう扱うか。
○ 今の意見に賛成である。私のプロジェクトでは、グローバル化の中で危機が 起こって、パブリックセクターがどう対応したかに興味がある。個別の企業でなく 産業としてこれにどう対応したか、それにあわせてパブリックセクターがどう対応 したかという面を膨らましていただけるとやりやすい。
○ 産業構造の変化は確かにこのプロジェクトでいままでやられていないところで ある。前言のパブリックセクターとは何を指すか。
○ 各国政府が持っている規制の権限があるが、これがグローバル化の中で有
効性を失ったり、規制の選択肢が狭まったりしている。パブリックセクターは戦
略 を考えねばならないが、その場合グローバルな変化と国内の産業構の
変化を両方見ながらやっていく。
○ そういう間題が当てはまるのは金融と情報通信で、他の産業はあまり当て はまらないかもしれない。
○ 金融制度改革は私のところも末廣・小森田プロジェクトも大きな柱である。産業 策を国がやり、ラテンアメリカなどは輸入代替工業化を長く続けたが、80年代にダ メになった。しかし全く消えたわけでなくいろいろな形で残っている。
○ 今のは非常に大きな問題で、各国政府がどれだけ政策のツールを持っているかは各省庁の編成にも反映しているであろうし、これをいちいちやるのは不可能かもしれない。具体的にできることは個別的な規制緩和政策などになるだろう。大滝プロジェクトでも、マクロの経済をつかまえるが産業政策としてはやりにくいのではないか。
○ とりあえず国内の経験からみると、国際化に対応するための産業政策としては、日本の場合50年代~60年代に出てきた。70年以降の金融セクターの間題はまさに中川氏の言われるようなことに当てはまり、これは最も重要なイシューである。
○ 末廣・小森田プロジェクトと中川プロジェクトに要請したい。政府と市場という二元論で切るケースが多いが、実際は政府がどれだけ出ていくかという場合企業というファクターを入れないとはっきっりしない。企業と市場の関係を見て政府の出方が親定されている。途上国の場合、市場のプレーヤーの間題をどうビルトインしていくかという間題が今後起こってくるのではないか。この視点をもう少し入れていただきたい。
○ 明日からハワイ大の、東アジアにおける企業の多国籍的展開というテーマで研究している研究者と会い、共同研究として組めるかどうか相談する。政府の政策を見る場合に抽象的なものでなく、具体的なターゲットとなっている企業の間題はもちろん念頭にある。政策の有効性を見る場合でも企業単位のビヘイビアなどは見る
つもりだ。
○ ドイツでは社会的市場経済という、個別的な企業には手を出さないというイデオロギーが形成され、戦後の産業政策のあり方は日本と全く違っていた。そういう場合もあるので、橘川氏が先ほど言われた、企業というファクターを入れなければ見えないというのは、やや日本的特質であるように思われる。
○ 中川氏に聞くが、一国間で収拾がつかないような、たとえば金融再規制など、国 際的な枠組みをもう一度作り直すというような間題も取り上げるのか。
○ それ自体をこのプロジェクトとして取り上げることはしない。やはり3つの地域の 経済改革が中心となる。
○ コアとの接点はどうつけるか。
○ 経済改革の中で金融制度改革は大きな柱であり、バブル以降の日本と比較で きる間題である。年金改革など社会保障改革も取り上げることになると思うが、これ ら3地域としては日本の例は一つの先例として関心が高い。
○ 国際的なネットワークの変化がアジアの国内の経済や金融の秩序構想とどう 関係しているかというような間題は私のところでもできるが、生産のネットワークの 変化については、橘川プロと末廣プロの連携で明らかにしてほしい間題である。
ドイツでも国内から企業がいなくなってしまうかもしれないなど、国境を越えた移 動 が大間題になっている。日本とアジアの関係が明らかになれば東欧とドイツの
関係を見る場合も参考になる。この場合のネットワークは国際分業の間題やテクノ ロジーの移転も含む。
○ Ⅱの国際的枠組みに議諭が集中している。Ⅱ-2市場のグローバリゼーションについて補足すると、ソニーのような形でのグローバルな展開と、リーバイスのようなグローバルオペレーションの二つが柱になる。Ⅱ-1に先ほどの金融や情報・通信の話が入る。しかし社研のメンバーで直接これをやっている人はいない。大滝プロジェクトとも中村(圭)プロジェクトとも統合再編が必要かもしれない。これからは互いのプロジェクトにもっと踏み込んで整理・統合をはかっていく必要がある。
○ 私のところは末廣・小森田プロと重なるし、中国とも一部重なるかもしれない。 コアとはリファレンスという形で協力でき、最終成果の日本のチャプターの執筆を頼 むことになるかもしれない。
○ 西ヨーロッパはどう組むか。末廣・小森田プロとも樋渡プロとも関係する。橘川、 大滝プロは純日本的で、樋渡プロは国際関係中心だがここの関係をどうつけられる だろうか。
○ 樋渡Iの中で、日本とドイツの比較という関心でやりたいと思う。
○ コア同士の関係はあまり間題がない。国際関係や外国をやってもあくまで関心 は日本にある。
○ 私もイギリスのことを報告したが、根にある関心は日本の間題である。EU統合の話は我々のところで直接には出てこない。国際的枠組みが一国内の間題に影響を与え、国内の変化がまた国際にはねかえる、というところで地域統合間題が生かせるかもしれない。
○ 3人でこういうプロスペクタスを出した含意の一つは、今までの報告を聞いておおよそ共通に扱うと思われ、かつ90年代の日本を考える際に欠かせない5つのターゲット--①国際的枠組み、②金融、③人的資源、④政府の役割、⑤社会について、各プロジェクトがいろいろなディシプリン、切り口から取り組み、それぞれ自分たちの切り口からこれらを見て何がいえるか、というところで整理し、重ね合わせる、ということを意図した。
○ 5つのターゲットで関心を重ねるという場合、たとえば金融で重なるのは具体的には金融制度改革、人的資源で重なるのは雇用間題、社会で重なっているのは福祉制度である。これらについてはこれからプロジェクトを進めていく過程で、何回か互いに考えていること、インフォーメイションを交換し合い、共有したり調整することが必要である。
○ いずれにしても今日行ったような議諭をもっと多くの参加者でやる必要がある。 それをコロキウムの場で行う。
*2月22日 各連携プロジェクトリーダーとコアプロジェクトの3人が10分ずつ中身の報告を行い、それをめぐってフリートーキングをする。できるだけ所員全員に出席を要請する。
・1月末までにコアの3人は、上記の議論をふまえ、連携プロジェクトへの呼びかけをより意識したものにプロスペクタスを修正し、それを連携プロジェクトリーダーに配って、問題意識を共有してもらう。
・連携プロジェクトリーダーは、5点の共通対象について問題意識の共有をはかるべく計画を練り直し、この面がはっきりするようなペーパーをあらかじめ提出して当日に臨む。 ・海外出張等で出席できないリーダーには、できればVTRでプレゼンテイションしてもらう。
*3月21日 2月のフリートーキングをふまえてコロキウムを開催する。
コアの3人が報告し、橋本壽朗氏がコメントする。
所外の研究者にもコメントを依頼する。(未定)
*4月4日 末廣・小森田プロジェクトで、東欧(ポーランド、ハンガリー)の研究者を招いてセミナーを行う。
テーマ 「東欧の経済改革」
|